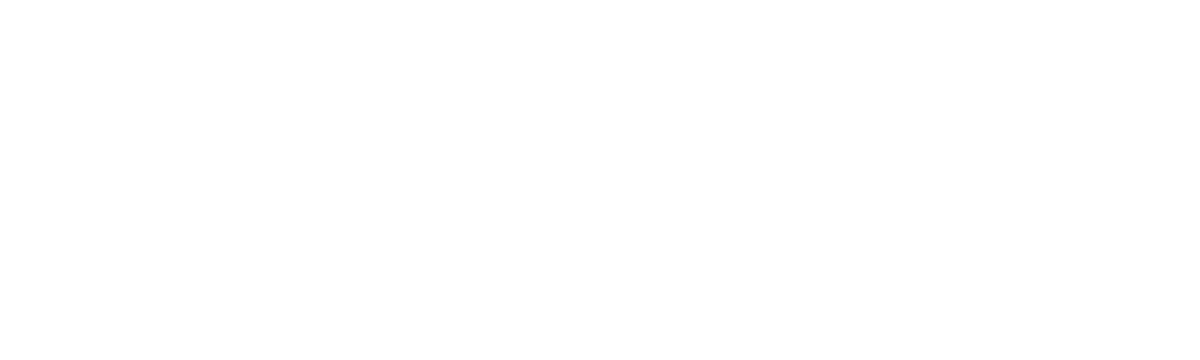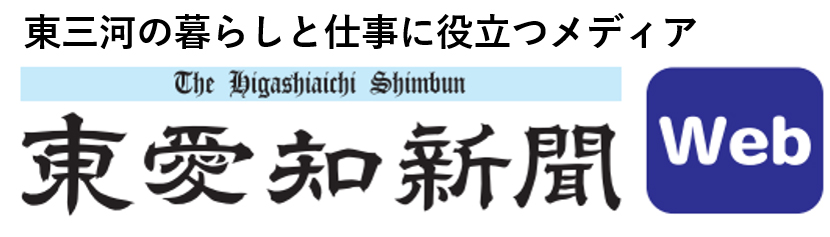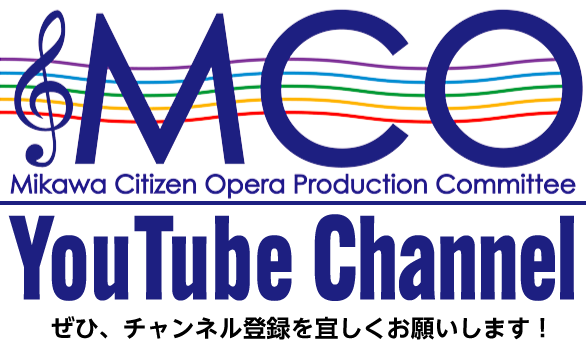Headline News
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載⑧

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈8〉
命懸け成し遂げた奇跡
(テノール・樋口達哉)
三河市民オペラを語るには、この人なしには語れない。鈴木伊能勢。
オペラ制作委員会の委員長であり、三河市民オペラの長(おさ)。彼への信頼、尊敬こそが20年という時を超えて今に至るのだろう。
シェニエ役を歌いたい一心でオーディションに参加。それが、僕と「三河市民オペラ」との出合いです。大作を手がける団体、しかも第一線で活躍する歌手たちが出演しているということで、以前よりその名が知られていました。
正直、はじめは一地方都市の「市民オペラ」としか思っていませんでした。しかし、彼らと時間を共有するとともにその思いはみるみる変わっていくのです。
彼らの素晴らしいところは、「チケットの完売ではなく、満席の会場!」という心意気。コンサートやオペラでよく見受けられるのが、チケットは完売だが空席が目立つ会場。その理由はさまざまですが、「完売」と「満席」とでは全く違います。本番までのプロセスとして、レクチャー講座を開催することも集客につながる要因の一つでしょう。
そして、「お客さまだけに感動を与えるのではない、出演者を含む関係者すべてが幸せになること」という信念。会場いっぱいに鳴り響く盛大な拍手とブラーボー、そしてスタンディングオベーション! 客席の熱気は最高潮!! 僕自身も幸せを感じた瞬間でした。
立ち稽古の初日から合唱団の皆さんの目がキラキラと輝いていて、発するエネルギーはハンパなく熱く、役が生きているのです。
本番では、合唱団を含む共演者、スタッフ、そして会場の熱気にのせられて、まるで自分にシェニエが憑依(ひょうい)したかのように、舞台上には「アンドレア・シェニエ」が立っていました。
その成功を支えたのが、伊能勢さんを中心とした「三河市民オペラ制作委員会」のメンバーの皆さん。彼らのオペラ制作への情熱、世界観、挑戦し続ける志の高さ…。僕の知る限り、これほどまでに意識の高い市民オペラはありません。彼らがいなければ間違いなく公演の成功は無かったでしょう。公演を終えて改めてその偉大さに気付かされました。
まさに命を懸けて、オペラ公演を成功に導くためのいかなる苦労もいとわない。アマチュアだからこその熱量で成し遂げた奇跡がそこにはありました。
30年近くオペラの現場に携わっている身として、改めて確信した「オペラ」という総合芸術の大きな可能性。
全国のオペラ歌手に伝えたい。
一度、この団体と共演してほしい。
そして、全国のオペラ・ファンに伝えたい!
一度でいいから、この団体の公演を観に来てほしい!
公演が終わった当初は、この舞台を全国展開できないものかと切に願いました。
しかし、それは違うのだと今は思えます。
この豊橋、三河の地で地元の皆さんが携わってこそ意味があるのではないでしょうか。
このビジネスモデルは、今後あらゆる作品をも成功させていくに違いありません。伊能勢さんを核として、我々はこれからのどんな困難をも乗り越えて行ける!
「三河市民オペラの冒険」はどこまでも続いて行くのです。
◇
福島県出身。日本を代表するテノール。武蔵野音楽大学卒業、同大学院修了後に渡伊。ハンガリー国立歌劇場「ラ・ボエーム」でヨーロッパ・デビューを果たし、翌年にはオペラ界の最高峰とされるミラノ・スカラ座に出演。その後、メトロポリタン歌劇場管弦楽団(ニューヨーク)をはじめとする多くのオーケストラと共演。その他、ミラノ大聖堂、サン・ピエトロ大聖堂(ヴァチカン)等のコンサートでも成功をおさめる。国内では新国立劇場、二期会を中心に「蝶々夫人」「椿姫」「トスカ」「トゥーランドット」「カルメン」などで主演し、その抜群の存在感は宮本亞門など名だたる演出家、指揮者からも多大な評価を得ている。コンサートでも「第九」はもとより、オペラ界のスターが一同に集まる「NHKニューイヤー・オペラコンサート」等で活躍。東京藝術大学、武蔵野音楽大学講師。二期会会員。オンライン・サロン「ヒグタツ倶楽部」を開設。
東愛知新聞にて新連載が始まりました
三河市民オペラの冒険と題しましての連載 Extra 番外編

【連載・EXTRA 番外編】特別寄稿「観客もオペラの一部になれる場」
(中日新聞記者 南拡大朗)
紙面の上にカーソル重ねますと拡大されます
下部に同じ文面を横書テキストにても掲示してございます


私が三河市民オペラを観たのは前回2023年の「アンドレア・シェニエ」が初めてで、その時に忘れられない光景がある。
もちろん舞台も感動したのだが、それとは別に往きの電車の中でのこと。豊橋駅でJRから豊橋鉄道渥美線に乗り換えると、同じ車内で揺られている人たちの中から「市民オペラ」という言葉が何度も聞こえてきたのだ。
あまりによく響くので声の主を探すと、数人のグループで来ている初老の男性だった。話題にしている詳しい内容は分からないが、口調からとにかく楽しそうな雰囲気が伝わってきて、ビジターとして一人押し黙っていた私の気分を高揚させた。
「これからオペラに行くんだ」という空気があの列車内には満ち、まだ観ぬ舞台にぐっと引き寄せられたような気がした。こんなこと、新宿駅からの京王線ではまず起こりえないと思う。
終演後も、舞台衣装のままの歌手たちがロビーに出て写真撮影に応じていて、感動の余韻がずっと続いた。この三河市民オペラの公演では、ただ観に行ったという以上に、観客として自分もオペラに参加した、オペラの一部になった、という気がしたのだった。
この「観客が参加した気分になる」という経験は、実は音楽文化にとって意外と重要なことなのではないかと、私はここ何年か考えている。
そこで思い出すのは、私がときどき読み返しているニュージーランド生まれの音楽学者クリストファー・スモールによる『ミュージッキング 音楽は〈行為〉である』(野澤豊一・西島千尋訳)という本だ。そこには、音楽の本質は作品そのものではなく、パフォーマンス(表現)をする行為にあり、それは舞台に上がる人だけでなく、観客も作曲家も、チケットの「もぎり」の人、楽器を運ぶ人、会場の掃除をする人も、その場にいるあらゆる人が一緒になって行っているのだ、と書いてある。
この本を初めて読んだときに私は大変感動したのだが、三河市民オペラの制作に関わっている人、毎回足を運んでいる人たちにしてみたら、「そんなこと当たり前じゃないか」と思われるかもしれない。だとしたら、豊橋を中心とした東三河にオペラ文化が立派に根づいている証拠だ。私が豊橋鉄道の車内で見かけたおしゃべりな人も、きっと自分たちがただその日だけの消費者、傍観者だなんて思ってはいないはずだ。
なぜ、一度行っただけでこんなに印象に残っているのか。もちろん日本を代表するすごい歌手たちが舞台に上がっているということもあるが、運営している根本姿勢が「いいものを見せてやってる」という上から目線でも、「とにかく有名なものを見たい」という消費者目線のどちらでもないからだろう。むしろ、神社の神事の余興として行われるお祭りに近い発想なのかもしれない。
お祭りには住民しか参加しない小規模なものもあれば、観光客が大勢訪れる有名なものまでさまざまだ。しかも、濃淡さまざまな参加者が連なっていて、どれもきちんとした文化だと内外で認識されている。一方で、クラシック音楽に目を向けると、20世紀の終わり以降、多額のお金がつぎ込まれながらも文化として定着せず、一過性で消えていった事例はたくさんある。文化として浸透しないのは、「上から目線」と「消費者目線」しかないことが原因だと私は考えている。
日本のお祭りと西洋の音楽が見事な形で合体し、持続しているのが三河市民オペラなのだとしたら、地域の文化として理想の形が見えてくる。ただ、お祭りは規模が大きくなればなるほどお金がかかり、地域だけで完結するのが難しくなる。資金面から見ても三河市民オペラが背負っている苦労は相当なものだと容易に想像がつく。
大きなお祭りだったら観光客のような外部から来る人に助けてもらう、というのが1つだと思うが、オペラをはじめホールで行う舞台芸術はキャパシティはそれほど多くない。スポーツの試合やポピュラー音楽のライブほどには大勢の人を一度に集められないのが難しいところだ。
人口減少で日本の舞台芸術全般が苦境にある今、屋台骨として支えるコアメンバーがいて、濃淡さまざまな人が関わって独自に運営されてきた三河市民オペラがどのような道をたどるのか。アイデアと行動に今後も注目していきたい。
◇
2006年に中日新聞社に入社し、現在は名古屋本社文化芸能部で音楽や文化政策などを担当。音楽家へのインタビューのほか、近年は地域の劇場・ホールの動向も取材している。ベテランのピアノ調律師を取材した「鍵盤に魔法を」を連載中。