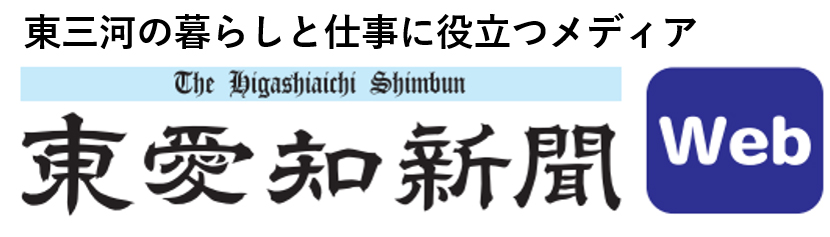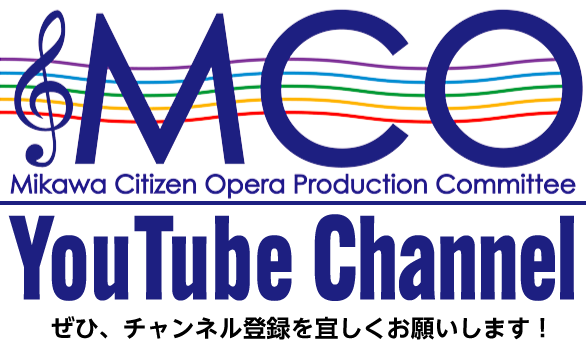Headline News
東愛知新聞にて新連載が始まりました
三河市民オペラの冒険と題しましての連載 Extra 番外編

【連載・EXTRA 番外編】特別寄稿「観客もオペラの一部になれる場」
(中日新聞記者 南拡大朗)
紙面の上にカーソル重ねますと拡大されます
下部に同じ文面を横書テキストにても掲示してございます


私が三河市民オペラを観たのは前回2023年の「アンドレア・シェニエ」が初めてで、その時に忘れられない光景がある。
もちろん舞台も感動したのだが、それとは別に往きの電車の中でのこと。豊橋駅でJRから豊橋鉄道渥美線に乗り換えると、同じ車内で揺られている人たちの中から「市民オペラ」という言葉が何度も聞こえてきたのだ。
あまりによく響くので声の主を探すと、数人のグループで来ている初老の男性だった。話題にしている詳しい内容は分からないが、口調からとにかく楽しそうな雰囲気が伝わってきて、ビジターとして一人押し黙っていた私の気分を高揚させた。
「これからオペラに行くんだ」という空気があの列車内には満ち、まだ観ぬ舞台にぐっと引き寄せられたような気がした。こんなこと、新宿駅からの京王線ではまず起こりえないと思う。
終演後も、舞台衣装のままの歌手たちがロビーに出て写真撮影に応じていて、感動の余韻がずっと続いた。この三河市民オペラの公演では、ただ観に行ったという以上に、観客として自分もオペラに参加した、オペラの一部になった、という気がしたのだった。
この「観客が参加した気分になる」という経験は、実は音楽文化にとって意外と重要なことなのではないかと、私はここ何年か考えている。
そこで思い出すのは、私がときどき読み返しているニュージーランド生まれの音楽学者クリストファー・スモールによる『ミュージッキング 音楽は〈行為〉である』(野澤豊一・西島千尋訳)という本だ。そこには、音楽の本質は作品そのものではなく、パフォーマンス(表現)をする行為にあり、それは舞台に上がる人だけでなく、観客も作曲家も、チケットの「もぎり」の人、楽器を運ぶ人、会場の掃除をする人も、その場にいるあらゆる人が一緒になって行っているのだ、と書いてある。
この本を初めて読んだときに私は大変感動したのだが、三河市民オペラの制作に関わっている人、毎回足を運んでいる人たちにしてみたら、「そんなこと当たり前じゃないか」と思われるかもしれない。だとしたら、豊橋を中心とした東三河にオペラ文化が立派に根づいている証拠だ。私が豊橋鉄道の車内で見かけたおしゃべりな人も、きっと自分たちがただその日だけの消費者、傍観者だなんて思ってはいないはずだ。
なぜ、一度行っただけでこんなに印象に残っているのか。もちろん日本を代表するすごい歌手たちが舞台に上がっているということもあるが、運営している根本姿勢が「いいものを見せてやってる」という上から目線でも、「とにかく有名なものを見たい」という消費者目線のどちらでもないからだろう。むしろ、神社の神事の余興として行われるお祭りに近い発想なのかもしれない。
お祭りには住民しか参加しない小規模なものもあれば、観光客が大勢訪れる有名なものまでさまざまだ。しかも、濃淡さまざまな参加者が連なっていて、どれもきちんとした文化だと内外で認識されている。一方で、クラシック音楽に目を向けると、20世紀の終わり以降、多額のお金がつぎ込まれながらも文化として定着せず、一過性で消えていった事例はたくさんある。文化として浸透しないのは、「上から目線」と「消費者目線」しかないことが原因だと私は考えている。
日本のお祭りと西洋の音楽が見事な形で合体し、持続しているのが三河市民オペラなのだとしたら、地域の文化として理想の形が見えてくる。ただ、お祭りは規模が大きくなればなるほどお金がかかり、地域だけで完結するのが難しくなる。資金面から見ても三河市民オペラが背負っている苦労は相当なものだと容易に想像がつく。
大きなお祭りだったら観光客のような外部から来る人に助けてもらう、というのが1つだと思うが、オペラをはじめホールで行う舞台芸術はキャパシティはそれほど多くない。スポーツの試合やポピュラー音楽のライブほどには大勢の人を一度に集められないのが難しいところだ。
人口減少で日本の舞台芸術全般が苦境にある今、屋台骨として支えるコアメンバーがいて、濃淡さまざまな人が関わって独自に運営されてきた三河市民オペラがどのような道をたどるのか。アイデアと行動に今後も注目していきたい。
◇
2006年に中日新聞社に入社し、現在は名古屋本社文化芸能部で音楽や文化政策などを担当。音楽家へのインタビューのほか、近年は地域の劇場・ホールの動向も取材している。ベテランのピアノ調律師を取材した「鍵盤に魔法を」を連載中。
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載⑦

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈7〉
創造なくして継承なし
継承なくして創造なし
(西川流四世家元・西川千雅)
「すごいんです。ぜひ見てください」。いろいろな方から、何度も勧められた三河市民オペラ。
「市民◯◯」と聞くと「アマチュアの発表会」「完成度よりは参加者の満足度」「家族や友達が応援」…そんな固定観念を持っていた私に渡されたのが一冊の本「三河市民オペラの冒険(水曜社)」。
その解説には「成功する『市民オペラ』のための、感動のマニュアル。赤字は絶対に出さない!2840枚のチケット完売!素人集団の地元経済人たちの市民オペラ制作の記録」とある。かなりそそられる。
「名古屋をどり」という日本舞踊公演を、80年近く続けている、名古屋に本拠地を置く日本舞踊の流派を預かる身としては、放っておけないコピー。
そして一昨年「アンドレア・シェニエ」で実際に舞台を見ることになり、豊橋駅を降りた。タクシーに台数が少なく、次の女性お2人もそれらしい気配を出しているため「もしかしてオペラですか?」と声をかけ乗り合わせること。道すがら「そんなにすごいんですか?」「とにかくすごいんですよ」と、想像しようがない言葉で熱っぽく話す2人に、いよいよますます期待が膨らんだ。
さて本当の舞台は今どきに言えば「激アツ」だった。本で読んだ情熱あふれる制作陣、一年がかりで稽古した市民参加のコーラスは一人ひとりが演技力抜群、その勢いにのせられて、一流のプロたちによる最高のパフォーマンス。奇跡的な三つ巴で、超満員の観客は大熱狂。
ひとりの「魂の叫び」から始まったムーブメントは、こうして5回目の大成功を収めた。
しかしこの方法にはひとつの問題がある。
大いなる感動の燃料が、その燃料を燃やし切るほどの情熱、その源は「毎回解散」「失敗したらやめてしまう」という背水の陣の覚悟から来るもの。「今しかない」「後がない」「一回こっきり」の絶大なパワー。これは「システム化」「誰でもできる」「普遍化」とは相反する。事業承継にはつきもののジレンマ。
熱力学第二法則「エントロピー」では、水に熱いお湯を入れるといずれぬるくなる。何事も混ざって中和するという科学的法則で、これを社会学になぞらえると、いつまでも熱の高さを維持することはできない。
ここでファウンダーの制作委員長、鈴木伊能勢氏から聞いた言葉が思い浮かぶ。
「文明は残るけど、文化はその人が居なくなったら終わる」
三河市民オペラの文化は残って文明となるのか…。
たとえば各地にこの意思が伝染する、という考えがある。触発されて各地の市民オペラはおろか市民活動がこの「情熱」というものと向き合うと、いま低迷している日本は蘇るのではないだろうか。
我々西川流は「家元」という「熱源」を継承している。しかしながら熱の種類は時代とともに変わる。楽茶碗の家元は「不連続の連続」というらしい。実際に後進にテクニックを教えるのではないが、その意思は継承されていく。
なればこそ、この「三河市民オペラ」にインスパイアされた動きが継承されれば、この情熱を重要視する志が継承され、表面は時代とともに変わっていけばよいのではないか。
最後に西川流に残る言葉を、三河のチャレンジャーたちに贈りたい。
「創造なくして継承なし、継承なくして創造なし」
◇
西川千雅(かずまさ)
日本舞踊家・西川流四世家元。家元の家に生まれ、幼稚園から高校まではインターナショナルスクール、米国ニューヨークの美術大学を卒業、家業を継ぐ。昭和20年より続く「名古屋をどり」主催者を継承。岡崎市「グレート家康公葵武将隊」愛知県「あいち戦国姫隊」などの観光PR隊プロデュースや、名古屋市「やっとかめ文化祭」ディレクター。6大学で客員教授や非常勤講師、健康舞踊NOSSを主宰するため49歳で藤田医科大学で修士取得。